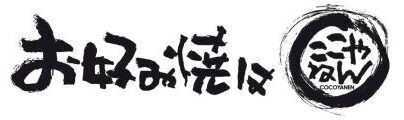ここやねん物語 – 不振店から繁盛フランチャイズへ
第1章|不振からの出発 ─ 三店舗の赤字からすべては始まった
「大赤字のお好み焼き屋を、なんとかしてくれへんか」
失業中だった私が“ここやねん”に出会ったのは、紹介会社を通じてのことでした。
面接で職務経歴書を見ていた創業社長が、開口一番こう言わはったんです。

「大赤字のお好み焼き屋を三店舗やっとるんや。
なんとか立て直して、ゆくゆくはフランチャイズにしたい。
あんた、やってくれへんやろか? 頼むわ!」
正直、戸惑いました。
お好み焼き屋の経営なんて、やったこともない。
けれど、その真剣な目を見たとき、こう思ったんです。
「逃げたらあかん。」
こうして、“ここやねん”再生の挑戦が始まりました。
どこにでもある「情熱だけの飲食店」
もともとこの会社は、健康食品の訪問販売からスタートし、
やがて宅配ピザのフランチャイズ展開で関西一円に広がっていました。
お好み焼き業態を始めたきっかけは、ある人の何気ない一言だったそうです。
「粉もんは儲かるで。」
その言葉が社長の耳に残って離れへんかった。
「ピザも粉もんやし、粉もんつながりでお好み焼き屋や!」
──そう言って始めたのが、“ここやねん”の原型でした。
けれど結果は、想像以上の大赤字。
勢いと情熱だけで突っ走った会社が、
いかにして“構造ある商売”に変わっていくのか。 物語はここから、本当の再生に向かっていきます。
成功体験が、新規事業の足かせになることもある
当時の宅配ピザ事業は、関西圏でそれなりの知名度があり、
オペレーションやマニュアルのノウハウも確立していました。
会社としての中心事業でもあったし、社内には「これまでの成功の型」がしっかり根づいていた。
でも、私が現場を見て感じたのは、
“成功ノウハウが新しい業態の足かせになる”という現実でした。
ピザもお好み焼きも、どちらも粉もんで丸い食べ物。
一見、似ているようでいて、商売の性質はまったく別物です。
宅配はスピードと物流効率が命やけど、
店舗型の飲食は、現場の空気とお客さんとの関係性がすべて。
経営哲学という「根っこ」は同じでも、
成果を出すためのディテールは、ぜんぜん違う。
“過去の成功”をそのまま持ち込むと、新しい現場では“誤った正解”になる──。
それを肌で感じたとき、私は初めて、「この再生はゼロから組み直さなあかん」と腹をくくりました。
売上はあるのに、利益が出ない──その正体は「構造赤字」
最初に任されたのは、赤字の三店舗を立て直すこと。
どの店もそれなりにお客さんは入っているのに、なぜか利益が出ない。
数字を見てもピンとこない。
私はまず、現場に足を運ぶことにしました。
昼から夜まで厨房に入り、ホールにも立ち、
一日の動きをすべてノートに書き出しました。
材料の仕入れ、仕込み、調理工程、在庫、発注、人の動き──。
やっていることは一つひとつまじめやのに、全体で見ると「ムダ」と「ムラ」が積み重なっていたんです。
たとえば、生のエビを仕入れて店でボイルして、殻をむいて仕込む。
新鮮でええように見えて、仕込みに人が取られすぎて人件費が膨らむ。
原価は下がっても、トータルでは赤字になる。
みんな“お客様のため”を思って頑張ってるだけに、余計に切なかった。
当時の店長が言っていました。
「売上はええんです。
でも、売っても売っても赤字が増えるんです。
出口が見えへん。」
その言葉が胸に刺さりました。
頑張るほど苦しくなる商売は、どこか構造がおかしい。
「これはセンスとか根性の話やない。構造の問題や。」
そう気づいた瞬間、霧が少し晴れた気がしました。
努力の量ではなく、「方向」を整える
まずは、何を残して何を変えるかを整理した。
売上を生む“ええ仕組み”と、赤字を生む“悪い癖”を分けて書き出す。
数字で見てみると、変えるべきところは意外とはっきりしていた。
「お客さんを喜ばせたい」
「手間を惜しまず良いものを出したい」──
その気持ちはそのまま残してええ。
ただし、それを“儲かる形”に変えなあかん。
経営というのは、努力の量やなくて、
努力の方向をどう整えるかや。
このとき、私は心の中でつぶやきました。
「なんとかなる。いや、なんとかできる。」
その瞬間が、“ここやねん再生”の本当のスタートやったと思います。
“売上があっても利益が出ない”──
それは、どんな業態にも潜む“構造的赤字”かもしれません。
あなたにも、同じような課題を感じたことはありませんか?
第2章|ここにしかない“普通のお好み焼き”という哲学
お好み焼きの“味”を、仕組みに変える──
それが再生の第一歩でした。「構造を変える」と決めたとき、最初に取り組んだのは“味”でした。
お好み焼き屋の再生言うても、根っこはやっぱり“おいしさ”。
けれど、それを感覚やセンスだけに任せたら、商売は長続きせえへん。
おいしさも仕組みでつくる──そう考えたんです。
「高級」より「普通」を美味しくする
当時のメニューには、「本豚玉一番」という高級バージョンの豚玉がありました。
ええ肉を使って、見た目も立派。
けど、値段は高いし、仕入れも手間がかかる。
しかも、「うちの本当に美味しい豚玉はこっちです」と言うてしまったら、
“普通の豚玉”の立場はどうなるんや?──そう思いました。
お好み焼きは、家族連れでも、会社帰りでも、学校帰りでも食べに来られる。
つまり、“普通であること”こそがいちばんの強み。
「ここにしかない普通のお好み焼き」──
その言葉が、私の中で一本の軸になりました。
マーケティング流行りのマーケティングに頼らない
今どきのマーケティング論では、「ペルソナを設定して、ターゲットを絞って施策を打ちましょう」とよう言われます。
もちろん、それが有効な場面もあります。
けど、お好み焼き屋は違うんです。
うちの店では、親子三代で楽しそうに食事しているテーブルの隣で、サラリーマングループが居酒屋使いをしてはる。
そのまた隣には、若いカップルや学生グループ。
お好み焼きは、誰でも、どんな目的でも気軽に来られる“日常のごはん”なんです。
せやから、特定の層を狙うよりも、“誰でも来やすい店”“いつでも入りやすい味”を守ることが大事。
中心にあるのは「オールターゲットの幸福」やと思っています。
素材を変えるんやない、考え方を変えるんや
味を立て直すために、まずキャベツのカットを見直しました。
粗すぎると水が出てベチャッとする。
細かすぎると甘みが飛ぶ。
何ミリ刻みで変えるか、何十回も試作を重ねた。
生地も同じ。
「生地でボリュームを出す」発想をやめて、キャベツの甘みを引き立てる“軽い生地”に切り替えた。
そこに合わせたのが、合成着色料も保存料も使わない自然派ソース。
安全で安心できるだけやなくて、甘味と酸味のバランスが絶妙に整った。
どれも特別な材料を使ったわけやない。
やっているのは、普通のことを丁寧に突き詰める作業です。
けど、その「普通」を仕組みで再現できたとき、お客様が「ここやねんの豚玉は、なんか違う」と言うてくれるようになった。
焼きそばにも「ここやねんの流儀」を
もう一つ、差別化の要やったのが焼きそばです。
当時はほとんどの店が“蒸し麺”を使ってました。
それではどこにでもある焼きそばになる。
うちは思い切って、生麺をゆで上げてから焼く方式にした。
調理時間は長いし、生産性は下がる。
厨房も熱くなるし、茹で麺器のスペースも必要や。
でも、その代わり、モチモチした食感と香ばしさが段違い。
「ここにしかない焼きそば」をつくることは、“非効率を許容する勇気”でもあったんです。
味を仕組みに変える、それが“ここやねん流”
飲食はどうしても「職人の勘」や「現場の感覚」で動いてしまう。
でも、それやと店長が変われば味も変わる。
それではチェーンにならへん。
「なぜ美味しいのか」を言語化し、誰が焼いても同じ品質を保つ。
これが“ここやねん”の再生で一番大事なポイントでした。
「奇をてらうより、“普通”を極める。」それが、うちの味づくりの姿勢になったんです。
“何の変哲もない普通のお好み焼き”。
けど、それが“ここにしかない普通”になるように。
味を整えることは、経営を整えることでもありました。
第3章|儲かる店舗設計を科学する ― 25坪・家賃25万円の成功モデル
味の再構築が見えてきたころ、次に取りかかったのが“店舗の形”でした。
どれだけ商品が良くても、店の造りが非効率やと利益は出えへん。
売上だけを追いかけてもうまくいかんのは、まさにこの構造にあったんです。
3店舗の失敗が教えてくれたこと
最初に引き継いだ三店舗は、立地もデザインもバラバラでした。
駅前の狭小店舗もあれば、ロードサイドの大型店もある。
中には厨房が狭すぎて調理が回らん店もあった。
最初は「まず既存店を立て直してから」と思ってたんですが、店舗ごとに問題が違いすぎて、標準形が見えなかった。
そこで発想を切り替えたんです。
「ええとこを統合して、儲かる新しいモデルを一から作ったほうが早い。」
条件を決めて“儲かる設計”をつくる
まず立地。
駅前で25坪、家賃25万円。
この条件で投資回収3年ができれば、どこにでも出せる現実的なモデルになる。
家賃の相場から見ても2等立地。
でも、そこで利益が出せたら、物件の幅が広がる。
フランチャイズを考える上では、これが大きなポイントになる。
そしてここで決めたのが、「まずは標準形を確立してから出店を広げる」という方針です。
3店舗の良い部分と悪い部分を統合・整理し、駅前型とロードサイド型、それぞれで“儲かるプロトタイプ”を先につくる。
そして、その結果を旧店舗にも順次フィードバックしていく。
先に形をつくってから、数を増やす。
感覚で広げるより、構造を整えてから拡張する。
これが、のちにフランチャイズ展開の基礎になった考え方やと思います。
夜営業に絞った小型モデル
そこで新たに出店したのが4号店。
ランチ営業をやめ、夜営業に絞り込んだ。
営業時間を17時〜24時にすれば、社員1シフトで回せる。
店長一人と、育ったアルバイトリーダーで十分回せる設計や。
つまり、人件費を固定化せず、シフトと構造で利益を生み出すモデルをつくったんです。
厨房と客席、1cm単位の設計
オープンキッチンを店の入口に置いて、ガラス越しに調理の様子が見えるようにしました。
「何してるか分かる」安心感と、ライブ感を出したかった。
お客さんの目に見える緊張感が、厨房を清潔に保たせるんです。
厨房内は、動線を1cm単位で検討した。
調理の手が交差せず、最短距離で動ける配置。
メイン鉄板の正面で調理しながら、後ろを振り向けば冷蔵庫と下ごしらえ台。
さらにその奥に一品料理・洗い場を直線でつなぐ。
コンパクトで高効率、けど窮屈には見えない。
お客様から見たときも、スタッフが活き活きと働く姿が見える。
この配置が“儲かる店舗設計”の根っこになりました。
働く人を守る設備設計
厨房の鉄板は、火力が強いほど熱気がこもります。
夏場はサウナ状態。
汗を流しながら焼いている姿は、働く人もしんどいし、お客様も見ていて不安になります。
そこで導入したのが、強制排気型メイン鉄板。
鉄板下に排気ダクトを設けて、熱気を強制的に外に逃がす仕組みです。
初期投資はかかるけれど、作業環境が劇的に改善された。
これで社員の定着率も上がったんです。
この仕組みは鉄板メーカーと共同開発して、標準化しました。
以降、全店で同じ鉄板を使えるようになり、導入コストも下がっていった。
メイン鉄板そのものを改良する
さらに一歩踏み込んで、メイン鉄板そのものの改良にも取り組みました。
3サイズの標準形を作り、これを組み合わせることで店舗規模に応じた最適な設定ができるようにしたんです。
鉄板で何より重要なのは、バーナーのカロリー数と本数、そして鉄板の厚み。
職人さんが焼く高級鉄板焼き店では、レンガみたいに分厚い鉄板を使うこともあります。
けど、それは温度の安定こそあれ、温度コントロールには熟練の技が要る。
逆に薄すぎると、温度上昇は早いけど、食材を置いた瞬間に一気に下がってしまう。
これも扱いが難しい。
うちはフランチャイズ展開を前提にしている。
現場の主戦力はアルバイトスタッフや。
数時間の教育で、誰でも無理なく扱える厚み──(この数値は企業秘密ですが)
その“ちょうどええ”厚みを採用しました。
鉄板の厚み一つとっても、“職人の感覚”を“仕組み”に置き換える工夫が要る。
そういう細部の積み重ねが、現場に優しいフランチャイズを支えているんです。

客席設計にも“儲かる構造”を
厨房がコンパクトになれば、客席を広く取れる。
ただし、詰め込みすぎても落ち着かん。
解放感を残しながら、仕切りでプライバシーを確保する。
さらに、可動式のブラインドを導入して、4人席×2卓を、ブラインドを上げれば8人席にできる構造にした。
小さな工夫ですが、これで回転率と満足度を同時に上げられた。
こうした“儲かる設計”の積み重ねが、のちにフランチャイズ標準モデルの基盤になっていったんです。
飲食店は、感覚でつくるもんやと思われがちやけど、実は「設計と動線」で儲けが決まる。
人が動きやすい店は、数字も動きやすい。
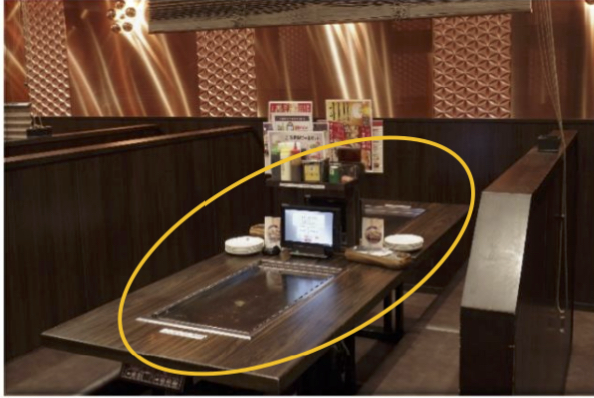

第4章|“京風もんじゃ”が拓いた、堅実な飲食フランチャイズ
「もんじゃ焼き」──
いまでは“ここやねん”の看板商品の一つですが、始まりは戦略でも計画でもありませんでした。
きっかけは、リーマンショックという逆風の中、現場の“遊び心”から生まれた小さな出来事でした。
リーマンショックと現場のひらめき
2008年、リーマンショックが起きて外食業界全体が冷え込みました。
“ここやねん”も例外ではなく、新規出店を一時凍結。
既存店の売上も伸び悩み、閉塞感が漂っていた。
そんな時、店長の一言が流れを変えました。
「煮詰まって考えても仕方ない。遊び心で何かやってみよや。」
その一言から、誰かがふと口にしたのが──
「もんじゃ焼きでもやってみましょうか?」
最初は軽い冗談のように聞こえた。
けれど実際にやってみると、少しずつ変化が起きたんです。
女性客が増えた。
口コミが広がった。
「もんじゃ焼きって名前は知ってるけど、食べたことがない。この店で食べられると聞いて来たんや」
という声も多く聞かれた。
関西で、もんじゃが受け入れられた理由
関西では、もんじゃを気軽に食べられる店は当時ほとんどなかった。
個人店で「メニューにありますよ」と言う程度。
だからこそ、女性グループが行動の中心になり、
“新しい体験”を求めて来店する動きが生まれていった。
これは単なるヒット商品ではなく、ブランドの“進化の兆し”でした。
焼き方を「お客様からスタッフ」へ変更
最初の頃は、東京スタイルに倣って「お客様が自分で焼く方式」でした。
焼き方のマニュアルをテーブルに置いて、「これを見て焼いてください」という形。
でも、関西ではそもそも焼いた経験がある人が少ない。
「難しそう」「自信がない」と感じる人が多く、注文数が伸びなかった。
そこで方針を変えました。
「スタッフが焼く」というスタイルです。
反対もありました。
「人件費が増える」「手が足りなくなる」──それでもやってみた。
結果は明らかでした。
お客様の満足度がぐんと上がり、スタッフも「焼くこと」が接客の一部になっていった。
焼く3〜4分間が、店を変えた
従業員が“もんじゃ焼き”をお客様のテーブルで焼くには、3〜4分ほどかかります。
たった数分ですが、手を動かしながら向かい合うこの時間が、お客様との距離を一気に縮めるんです。
「初めてもんじゃですか?」
「今日はどこから来はったんです?」
そんな何気ない会話が自然に生まれ、笑い声が広がっていく。
この3〜4分間が、“関係が生まれる時間”になっていった。
そして、ここで大きな副産物が見つかりました。
スタッフが「お客様の笑顔を自分の手で作れる」喜びを感じ始めたんです。
あるアルバイトはこう言いました。
「カップルのお客様やったんで、ハート型にして焼いたら、めっちゃ喜ばれたんです!」
この言葉を聞いた瞬間、私は胸の奥が熱くなりました。
生産性を上げようと、外食業界全体が機械化や効率化を進めてきた。
それは決して間違いではない。
でも、その過程で“人と人のつながり”というサービスの原点を私たちはどこかに置き忘れていたのかもしれない。
「ああ、これやな。」
店とお客様、スタッフ同士、そしてスタッフ自身の中に“やりがい”が戻ってきた。
これこそが、外食産業の本質やと感じた瞬間でした。

「東京の追随ではない」──“京風もんじゃ”誕生
もんじゃの評判が広がる中で、私は次の課題を感じていました。
「東京の真似ではなく、“ここやねん”らしいもんじゃにしたい。」
そうして始まったのが、“塩だれベース”の試作です。
きっかけは、あるSVの何気ない一言。
「ソースやなくて、塩だれで作ってみたら美味しいんちゃいます?」
やってみると、予想を超える味やった。
出汁の旨みが立ち、具材の風味が際立つ。
全員が「これや!」と声をそろえた。
「ほな、“京風もんじゃ”にしよか。」
「京風って、どんな定義なんです?」
「そんなもん、最初に言うたもん勝ちや!」
笑いの中から生まれた“京風もんじゃ”は、気取らず、けど芯のある“ここやねん流”の象徴になりました。
「東京の追随ではなく、関西の文化として育てる」──
それは自然なようで、実は当時誰もやっていなかった発想でした。

現場発の文化が、ブランドを変えた
こうして“京風もんじゃ”は全店に導入され、
売上だけでなくお客様の滞在価値と満足度を押し上げました。
焼きの手順、スタッフの立ち位置、会話のきっかけ──
そのすべてをマニュアル化し、教育プログラムに組み込んだ。
もんじゃを焼く3〜4分間を、“人と人をつなぐ時間”として再現できるようにしたんです。
偶然から始まった取り組みが、「人の心を仕組みに変える」フランチャイズの知恵へと進化した。
私はこのとき強く思いました。
仕組みを作ることは、人を機械のように動かすことではない。
仕組みは、人の温度を守るためにあるんや。
偶然のひらめきも、現場で磨けばブランドになる。
“京風もんじゃ”は、うちがそれを学んだ象徴やと思っています。
第5章|粉もん経営の真髄──ここやねん式フランチャイズ
外食業の世界では、流行と淘汰の波が絶え間なく押し寄せてきます。
その中で“ここやねん”が20年以上続いてきたのは、決して奇をてらったことをしてきたからやない。
「普通を極める」姿勢を、仕組みと人の両面で磨き続けてきたからやと思っています。
“味と仕組み”の両輪が生み出すおいしさ
うちは、お好み焼き・焼きそば・もんじゃという、どれも「粉もん」の王道を扱っています。
けれど、その“普通のメニュー”の中に、他店にはない「いつでも、どの店でも、同じ味と雰囲気で楽しめるおいしさ」を持たせてきました。
生地、キャベツ、ソース──すべての要素をミリ単位で設計し、オペレーションまで含めて“誰が焼いても同じように美味しい”を実現してきた。
だから、どの店舗でも安心して「ここやねんの味」を体験してもらえる。
これは、職人の感覚に頼った味ではなく、人の手で続けられるように設計された“商売としてのおいしさ”なんです。
同時に、厨房動線・鉄板設計・席配置など、店舗全体を科学的に利益が出る構造として最適化してきました。
25坪・家賃25万円・投資回収3年──
このモデルができたとき、「誰でも再現できるチェーン」が初めて見えた気がしました。
「人が主役」のフランチャイズ
どれだけ仕組みを整えても、動かすのは“人”です。
うちの店では、アルバイトスタッフが主戦力です。だからこそ、「誰がやっても同じ結果が出せる」環境づくりが大事になる。
教育プログラムやマニュアルはもちろん、POSデータや情報システムで現場の状態を可視化し、店長の判断を支える。
けど、数字の管理だけでは店は回らへん。
店の空気をつくるのは、現場にいる人の笑顔とやりがいやと思う。
“京風もんじゃ”の3〜4分間の焼きの時間が象徴するように、人が輝く仕組みこそが、フランチャイズの生命線やと思うんです。
うちでは店長を「経営者」として育てる方針を大事にしています。
本部が全部を決めてしまうのではなく、現場が考え、改善していく文化をつくる。
それが結果として、組織の持続性につながっている。
「派手さ」より「堅実さ」
今の世の中、“バズる店”や“話題のブランド”が一瞬で脚光を浴び、同じ速度で消えていくことも多い。
けれど、うちはそういうタイプのチェーンやない。
一店舗一店舗が地に足をつけて、地域のお客様に支持されながら着実に積み上げていく。
その堅実さが、結果として“強いフランチャイズ”を生む。
「大きくすることを考える前に、長く続けることに集中する。」
これが、うちの変わらぬ信条です。
派手さはないかもしれません。
けれど、真面目に商売を続けることの尊さを、この20年で何度も実感してきました。
仕組みは、人を縛るためにあるんやない
フランチャイズというと、
“マニュアルで縛る”とか“自由がない”という印象を持たれることがあります。
けど、うちが目指しているのはまったく逆です。
仕組みを整えるのは、人の自由を守るため。
決められた手順があるからこそ、人は迷わず、創意工夫にエネルギーを使える。
仕組みが人を支え、人が仕組みを育てる。
この循環が生まれたとき、フランチャイズは単なる「拡大の手段」ではなく、
「文化を広げる仕組み」になるんやと思っています。
“ここやねん式”という選択
お好み焼き・もんじゃ・鉄板焼。
どれも昔からある料理やけど、その「普通」を、今の時代にどう残すか。
うちの答えは、「構造と人を両立させる」ことでした。
マニュアルもデータも大事。
でも最後は、人の目と手と心がいる。
そして何より、どの店舗も「誰かの物語の舞台」になっている。
スタッフの成長、お客様との会話、地域のつながり。
その積み重ねこそが、“ここやねん”の本当のブランドやと思うんです。
粉もんは、人の心を混ぜて焼くもんや。
これは、今も変わらん。
“ここやねん”から始まる新しい挑戦へ
これからも店舗数を無理に増やすつもりはありません。
大事なのは、ひとつひとつの店が地域で愛され続けること。
そして、そこに関わる人たちが、「自分の店」と胸を張って言える仕組みを守ること。
「人を活かす構造」と「構造を活かす人」。
その両輪がまわり続ける限り、“ここやねん”の挑戦に終わりはありません。